新社会人の皆さん、初めての給与明細に「健康保険料」や「厚生年金保険料」という項目を見て、戸惑いを感じていませんか? 社会保険は大切ですが、それだけでは足りない部分もあります。医療費や長期の休職、将来の資産形成など、自分のライフスタイルに合わせて必要な保障を選ぶことが重要です。この記事では、社会保険とそれを補う民間保険についてわかりやすく解説します。
目次
はじめに – なぜ新社会人に保険が必要なのか
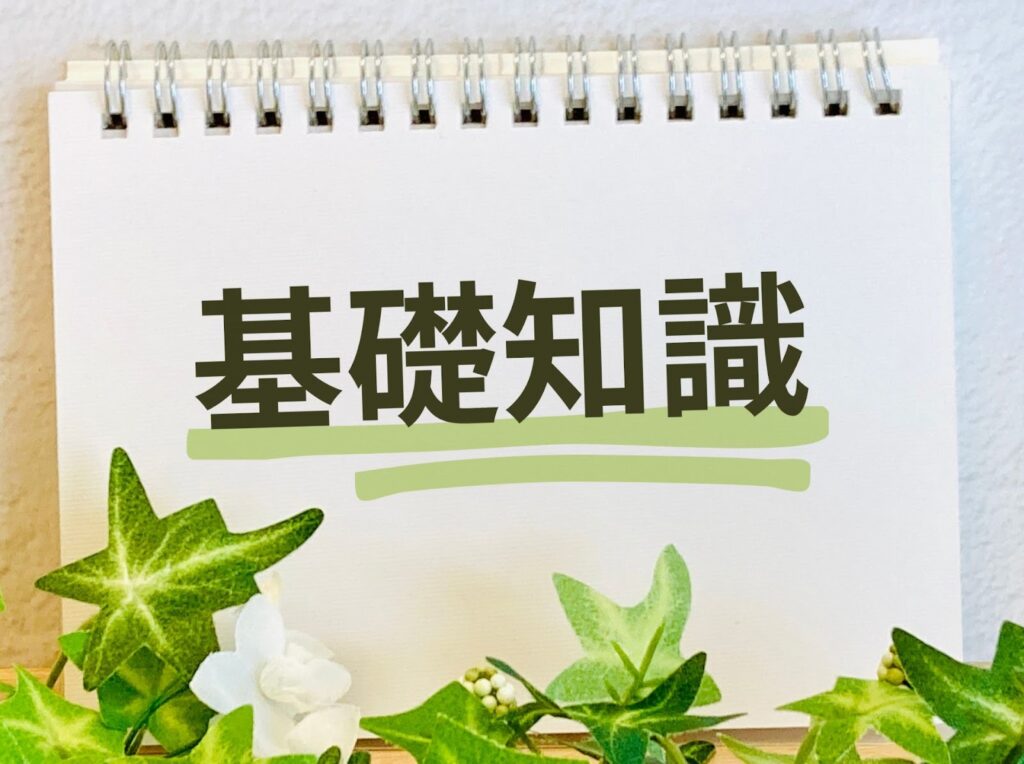
新社会人として初めて給与明細を手にすると、必ず「健康保険料」や「厚生年金保険料」といった項目が記載されています。これらは、国や企業が運営する社会保険に基づくものであり、病気やけがの際の医療費負担の軽減、将来の年金給付、失業時の支援など、最低限の生活を維持するための制度です。
しかし、社会保険はあくまで最低限の保障を提供する仕組みに過ぎず、備えとしては不十分な場合があります。その不足を補うために存在するのが、民間保険です。民間保険は、社会保険がカバーできない部分に対して、個々のライフスタイルやリスクに応じた保障を追加するための選択肢となります。
社会保険と民間保険の違いを理解する

社会保険とは何か
社会保険は、国が運営する公的な制度であり、会社員として働く全ての人が自動的に加入する仕組みです。主な保障内容は以下の通りです。
健康保険
- 医療機関での治療費の自己負担が原則3割に軽減される
- 高額な医療費が発生した場合は「高額療養費制度」により、一定額を超えた分が払い戻される
- 病気やケガで働けない期間に、生活を支えるための「傷病手当金」を給付
厚生年金保険
- 将来の生活を支えるための年金を受給できる
- 障害を負ったときや死亡した場合の遺族年金としても機能する
雇用保険
- 失業時に一定期間、給付金が支給される
労災保険
- 仕事中や通勤時の事故・けがに対する補償が受けられる
これらの制度は、企業が保険料の一部を負担しているため、個人の経済的負担を軽減する仕組みとなっています。
社会保険だけではカバーできない部分
社会保険は、国民全体の最低限の生活を守るために重要な役割を果たしていますが、すべてのリスクに柔軟に対応することはできません。例えば、入院や手術をした際の治療費に加え、差額ベッドの利用料、食事代、通院費などは健康保険では十分に補えません。
また、病気やけがで長期間働けなくなった場合、公的な傷病手当金は最長1年6か月までしか支給されないため、その後の収入の途絶えは深刻な問題となります。
さらに、老後の生活資金としての年金だけでは、現代の長寿化や生活水準の向上に対して十分とは言えず、自ら資産を形成する努力が必要となります。こうした点において、民間保険は社会保険が補えない部分を補強し、より安心した生活設計をサポートする役割を果たすのです。
医療保障 – 入院や手術、長期治療に備える
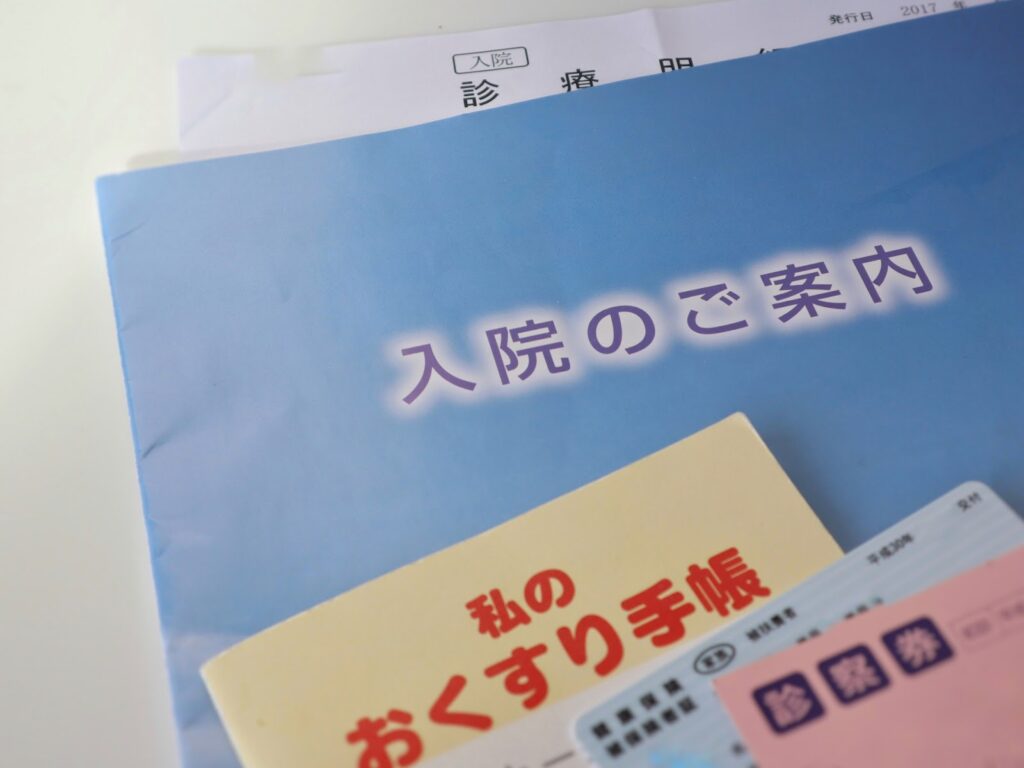
健康保険の限界と高額療養費制度の実情
健康保険に加入していれば医療費の自己負担は3割ですが、それだけでは入院や手術にかかるすべての費用をカバーすることはできません。
例えば入院や手術にかかる費用は、治療費だけではありません。差額ベッド代、食事代、日用品、交通費 などの自己負担が発生し、さらに長期間仕事を休むことで収入が減少する というリスクもあります。
高額療養費制度を利用すれば、一定額を超えた医療費の払い戻しを受けることはできますが、一時的に全額を支払う必要があるため、貯蓄が少ない新社会人にとっては大きな負担となる 場合があります。
新社会人は突発的な出費に対応しにくいため、高額な医療費や長期入院のリスクに備えておくことが重要です。
医療保険の役割と選び方
民間の医療保険では、入院給付金、手術給付金、退院後の通院保障 などが用意されており、公的な保障の不足を補うことができます。例えば差額ベッド代や食事代の負担、手術費用の一部をカバー、また退院後の治療やリハビリにかかる費用も補助される場合もあります。
特に新社会人は扶養家族がいないことが多いため、大きな死亡保障よりも入院や手術時の費用補償を優先するほうが理に適っています。さらに、若いうちに加入すると保険料が割安 になり、将来的な負担を軽減できるというメリットもあります。
新社会人が医療保険を選ぶ際は、入院給付金の日額、手術給付金の額、保障期間などを比較し、自分に合ったプランを選びましょう。健康なうちに加入すれば、保険料を抑えつつ将来的な保障を確保できるため、早めに検討してみてください。
就業不能保障 – 働けなくなったときの生活費を守る

「生きているのに働けない」ことがもたらす経済的リスク
少し乱暴な言い方ですが、保険の観点からみると、一番生活を逼迫するのは死亡でも病気でもなく「働けない状態」なのです。
病気やケガで長期間働けなくなると、毎月の給与が途絶えてしまいますが、家賃や光熱費、食費、スマホ代、ローンの支払いなど、生きていくための固定費は変わらず発生します。
公的な傷病手当金という制度を利用すれば、最長1年6か月間は給与の約3分の2が支給されますが、それだけでは十分な生活費を確保できないケースもあります。新社会人は、まだ貯蓄が十分でないことが多いため、収入が途絶えることは大きなリスクです。働けなくなる期間が長引けば長引くほど、経済的なダメージは深刻になり、最悪の場合は生活の維持が困難になることも考えられます。
所得補償保険で収入の減少に備える
こうしたリスクに備えるためにあるのが「就業不能保障(所得補償保険)」です。この保険は、働けなくなった場合に一定期間、給与の一部を給付金として受け取ることができます。
たとえば、病気やケガで6か月間働けなくなった場合、毎月20万円の給付金を受け取ることができる保険に加入していれば、公的な保障と合わせて、その間の家賃や生活費をカバーできます。このおかげで、生活の不安を軽減しながら治療に専念出来るのです。
新社会人にとって、「働けなくなること」は他人事のように思えるかもしれません。しかし、現実には病気やケガで仕事を長期間休まざるを得なくなるケースは意外と多く、誰にでも起こり得ることです。「健康だから大丈夫」と思うかもしれませんが、万が一のリスクに備えて、今のうちからしっかりと対策を考えておきましょう。
資産形成 – なぜ若いうちから始めるべきなのか
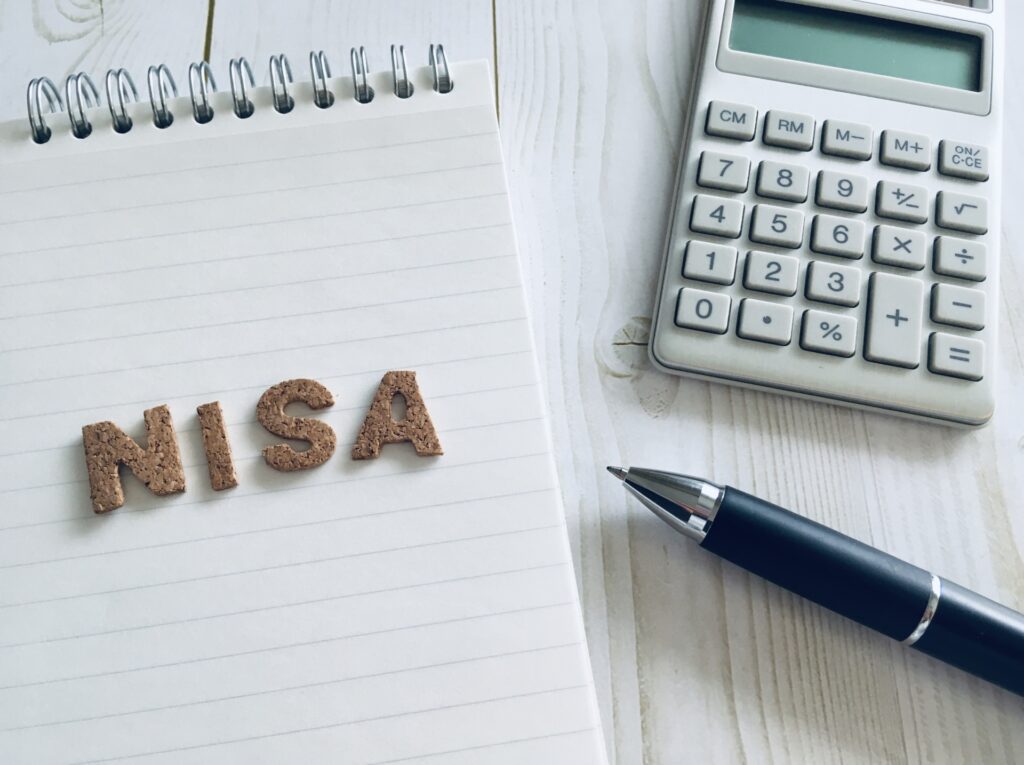
時間を味方につける資産運用のメリット
資産形成は、できるだけ早く始めることで大きな効果を発揮します。若いうちから少額でも積み立てを始めれば、時間をかけて複利効果が働き、長期的に見ると大きな資産に育てることができます。たとえば、同じ金額を積み立てる場合、20代で始めるのと30代で始めるのとでは、運用期間に10年以上の差が生じ、その差が将来の資産額に大きく影響します。資産形成の基盤を早期に築くことは、将来の生活の選択肢を広げ、安心して老後を迎えるための大切なステップとなります。
資産形成のための具体的な手段
若いうちから始める資産形成の手段として、iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)が注目されています。iDeCoは、掛金が全額所得控除の対象となるため、節税効果が期待できるとともに、老後資金を効率的に積み立てる手段となります。NISAは、運用益が非課税となるため、少額の投資からでも資産を増やす効果が期待できます。これらの制度は、国が後押しする制度であり、若いうちから計画的に利用することで、将来の安心に大きく貢献します。
また、場合によっては貯蓄型保険など、保険商品を活用して資産を形成する方法もありますが、その際は途中解約時のリスクや手数料、返戻金の変動などを十分に理解した上で選ぶ必要があります。
まとめ – 将来に向けた一歩を踏み出す
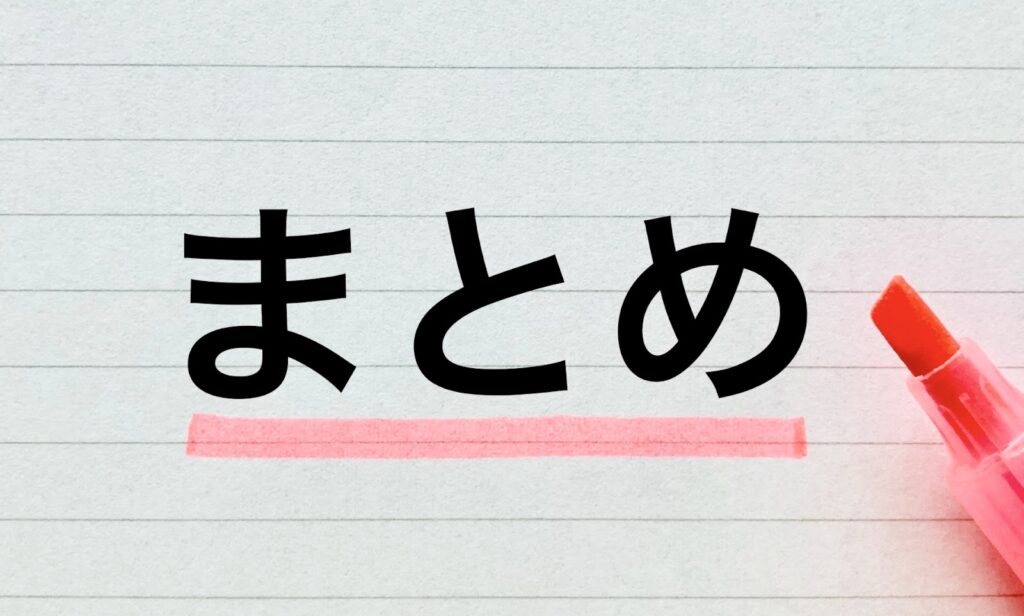
新社会人にとって、保険は将来の安心を得るための重要なツールです。とはいえ、「まだ若いから必要ない」と思うかもしれませんし、実際に今すぐ必要のない保障もあります。しかし、医療保障や就業不能保障、資産形成といった「将来に向けた備え」は、いざというときに大きな支えになります。
すべての保険に加入する必要はなく、自分にとって本当に必要なものを選ぶことが大切です。社会保険でどこまでカバーできるのかを理解し、不足する部分をどう補うかを考えましょう。
また、保険は一度入れば終わりではなく、ライフステージや収入の変化に合わせて見直していくものです。将来の選択肢を広げるためにも、今のうちから基本的な知識を身につけ、必要に応じて準備を始めてみましょう。
保険のライフアシストは、お客様一人ひとりに最適な保険プランを無料でご提案いたします。保険相談は1回2時間程度を目安に、経験豊富なスタッフが丁寧にご説明させていただきます。契約後のアフターフォローも充実しており、将来のライフプランに応じた保障の見直しもサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール

- 保険のライフアシスト|執行役員・営業企画推進部長
-
球技は苦手ですが身体を動かすことは大好きで、中学・高校では器械体操部に所属。
30歳代までモーグルスキーの草レースに参加していました。
一昨年は10年ぶりにスキーを再開し、今年もコブ斜面を楽しんでいます。
更にSUPにも目覚め、春から秋は湖で癒やされています。
また毎朝のラジオ体操が日課となっています。
タイマーセットしたラジオで目覚め、朝6:30から身体を動しています。
頭もスッキリと目覚めますのでオススメです!
でも例えどれだけ健康に気をつけていたとしても、いつ誰の身に何が起こるかはわかりません。
事実私もケガを含めて10回もの入院を経験しました。
そのような経験も保険業界に身を置く一つのきっかけです。
保険はもちろん、暮らしとお金にまつわる様々なお悩み、どうぞお気軽にご相談下さい。
最新の投稿
 保険の基礎知識2025年2月25日変額保険はやめたほうがいい?プロが解説する3つのリスクとメリット・デメリット
保険の基礎知識2025年2月25日変額保険はやめたほうがいい?プロが解説する3つのリスクとメリット・デメリット 保険の基礎知識2025年2月24日新社会人・新入社員の保険入門 本当に必要な保障と選び方を保険のプロが徹底解説
保険の基礎知識2025年2月24日新社会人・新入社員の保険入門 本当に必要な保障と選び方を保険のプロが徹底解説 保険の基礎知識2024年11月24日生命保険金の相続手続きガイド – 必要書類と手続きの流れを専門家が解説
保険の基礎知識2024年11月24日生命保険金の相続手続きガイド – 必要書類と手続きの流れを専門家が解説 保険の基礎知識2024年11月17日保険料控除の上限額は?生命保険と個人年金保険の控除限度を解説
保険の基礎知識2024年11月17日保険料控除の上限額は?生命保険と個人年金保険の控除限度を解説

コメント